ノロウイルスによる食中毒に注意しましょう
印刷 ページ番号1003409 更新日 2025年10月14日
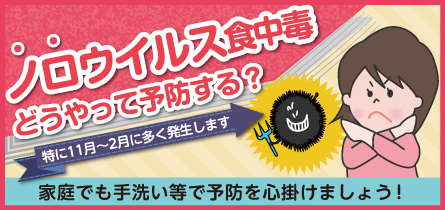
ノロウイルスによる食中毒は、年間食中毒患者数の約5割から6割を占めています。
特に11月から2月の冬季に多く発生し、主に、調理従事者を介した食品の汚染が原因と考えられます。
調理従事者はもちろん、ご家庭でも手洗い等での食中毒予防を心がけましょう。
ノロウイルスによる食中毒の特徴
- ノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒は、1年を通して発生していますが、特に冬季に流行します。
- 感染力が強く、10個から100個という少量で感染が起こります。(一方、患者の嘔吐物や便には1グラムあたり100万個から10億個もの大量のノロウイルスが含まれています。)
- 二枚貝の中腸腺に蓄えられていることがあります。
- 最近の食中毒事例では、ノロウイルスに感染した調理従事者が食品を汚染し、感染を拡大させる事例が多くなっています。
主な症状
- ウイルスが体内に取り込まれてから、24時間から48時間で発症します。(感染しても発症しない場合や軽い風邪のような症状の場合もあります。)
- 主な症状は、吐き気、おう吐、下痢、腹痛、軽度の発熱(38度以下)などです。
- 通常これらの症状が1日から2日続いたあと治癒しますが子どもやお年寄りなどでは重症化することがあります。
- 症状がなくなっても、1週間から長いときには1カ月程度、便の中にウイルスが排泄されることがあります。
ノロウイルスの感染経路
ノロウイルスの感染経路はほとんどが経口感染で、次の3つに分類されます。
経路1 食品から人へ(食中毒)
- 汚染されていた二枚貝を、生あるいは十分に加熱調理しないで食べた場合
- ノロウイルスに汚染された井戸水や簡易水道を消毒不十分で摂取した場合
経路2 人から食品を介して人へ(食中毒)
- 食品取扱者(食品の製造等に従事する者、飲食店における調理従事者、家庭で調理を行う者などが含まれます。)が感染しており、その者を介して汚染した食品を食べた場合
(注)このように、食品取扱者を介してウイルスに汚染された食品を原因とする事例が近年増加しています。
経路3 人から人へ(感染症)
- 家庭や共同生活施設などヒト同士の接触する機会が多いところで飛沫感染等直接感染する場合
- 患者のノロウイルスが大量に含まれるふん便や吐ぶつから人の手などを介して二次感染した場合
(注)ノロウイルスは食品や水を介した食中毒の原因になるばかりでなくウイルス性胃腸炎(感染症)の原因にもなります。
どうやって予防するの?
1 手洗い
2度洗いが効果的です。適切なタイミングで丁寧に洗いましょう。
- トイレの後、調理する際、食事の前にはよく手を洗いましょう。
- 手洗いの後、使用するタオル等は清潔なものを使用しましょう。
- 手洗いの方法など、詳しくは、下記「関連情報」のリンク先をご覧ください。
2 加熱
85度から90度以上で90秒以上の加熱をしましょう。
- 加熱が必要な食品(特にカキなどの二枚貝など)を加熱する場合は、中心部まで十分に加熱してから食べましょう。
- 湯通し程度の加熱では、ノロウイルスは死にません。
3 消毒
調理器具は、十分に洗浄した後、熱湯(85度1分間以上)や塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)で消毒しま しょう。
- 消毒液は時間が経つと効果が減っていきます。使用する直前に作り、早めに使いきるようにしましょう。
- 消毒液を保管する場合は、誤って飲むことがないように、消毒液と明記して保管しましょう。
- 消毒液の作り方など、詳しくは、添付ファイルをご覧ください。
二次感染を予防するために・・・
ノロウイルスによる感染を広げないため、下痢やおう吐物の処理を適切に行いましょう。
- 便やおう吐物を処理するときは、使い捨てのエプロン・マスク・手袋等を着用しましょう。
- 便やおう吐物に汚染された場所は、塩素系漂白剤を含ませた布で被い、しばらくそのまま放置して消毒しましょう。
- ドアノブ、蛇口、手すり、子どものおもちゃなど、感染した人が「手を触れるところ」にもウイルスが付着する可能性があります。消毒液を染み込ませたペーパータオル等で消毒しましょう。
- 処理した後は、よく手を洗い、うがいをしましょう。
- 下痢などの症状がある人は、一番最後にお風呂に入るか、シャワーのみにしましょう。
- おう吐物や、便で汚れた衣類等は消毒したあと、他の衣類とは分けて洗いましょう。
嘔吐物処理のリーフレットについては、添付ファイルをご覧ください。
食品を取り扱う営業者の方へ
不顕性感染者を前提とした対策が重要です。
1 ノロウイルスを持ち込まない
- 常日頃から、ノロウイルスに感染しないように心がけましょう。
- 感染したら仕事を休みましょう。
- 感染後は、検便でノロウイルスを保有していないことを確認してから調理作業に復帰しましょう。
- 手洗い、うがいを励行しましょう。
- 従事者の健康状態の把握、管理を行いましょう。
- 従事者専用のトイレを設置し、専用の履物を設けましょう。
- 二枚貝の取扱いに注意しましょう。
- 施設利用者に対する注意喚起を行いましょう。
2 ノロウイルスを拡げない
- トイレ後、清掃後及び入室前等の適切な手洗いを実施しましょう。
- 施設の日常的な清掃、消毒を実施しましょう。
- 調理時の交差汚染を防止しましょう。(加熱後食品の取扱い・調理器具の消毒)
- 嘔吐物の適切な処理をしましょう。
3 ノロウイルスをやっつける
- 中心温度85度から90度で90秒以上の加熱を行いましょう。
- 中心温度計での測定が効果的です。
4 ノロウイルスを食品につけない
- 作業前の手洗いを徹底しましょう。
- 素手で食品に触れないようにしましょう。
- 使い捨て手袋やマスクを正しく着用し、衛生的な作業着を着用しましょう。
- 調理器具の洗浄及び消毒を徹底しましょう。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp














