障害福祉サービス・障害児通所支援等を利用したときの費用
印刷 ページ番号1004233 更新日 2022年12月7日
サービスにかかる費用の負担割合
サービスを利用した方は、サービスにかかる費用の1割相当額を支払います。ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっている他、いろいろな負担軽減のしくみがあります。また、利用者負担の1割相当額を除いた額は市などが負担するしくみです。
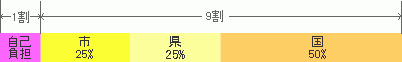
なお、施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは自己負担になります。
障害福祉サービスでの世帯の範囲
障害福祉サービスでの世帯の範囲は、サービス利用者が18歳以上のときは本人および配偶者を、サービス利用者が18歳未満のときは住民基本台帳上の世帯をさします。
利用者負担上限月額について(平成24年4月1日現在)
所得に応じて区分が分けられ、それぞれに負担の上限額が決められています。
|
所得区分 |
対象となる方 |
上限額(月額) |
|---|---|---|
|
生活保護 |
生活保護世帯の方 | 0円(自己負担なし) |
|
低所得1 |
市町村民税非課税世帯で障害者または障害児の保護者の年収が80万円以下の方 |
0円(自己負担なし) |
|
低所得2 |
市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない方 | 0円(自己負担なし) |
|
一般 |
市町村民税課税世帯の方 | 37,200円 |
障害福祉サービスの利用者負担の軽減
障害者(18歳以上)の利用者負担の軽減
居宅で生活する障害者で、所得が低い方は、居宅、通所サービスの負担上限額が軽減されます。
|
所得区分 |
負担上限額(月額) |
|---|---|
|
生活保護、低所得1、低所得2 |
0円(利用者負担なし) |
|
一般(市町村民税所得割額16万円未満) |
9,300円 |
(注意)負担上限月額を判定するための所得区分認定については、世帯ではなく「本人および配偶者」のみの所得で判断されます。
入所施設およびグループホーム等を利用する障害者で、所得が低い方は、負担上限額が軽減されます。(20歳以上)
|
所得区分 |
負担上限額(月額) |
|---|---|
|
生活保護、低所得1、低所得2 |
0円(利用者負担なし)※療養介護医療を除く |
障害児(18歳未満)利用者負担の軽減
障害児の居宅、通所サービスの負担上限額が軽減されます。
|
所得区分 |
負担上限額(月額) |
|---|---|
|
生活保護、低所得1、低所得2 |
0円(利用者負担なし)※肢体不自由児通所医療を除く |
|
一般(市町村民税所得割額28万円未満) |
4,600円 |
20歳未満の施設入所者への利用者負担の軽減
|
所得区分 |
負担上限額(月額) |
|---|---|
|
生活保護、低所得1、低所得2 |
0円(利用者負担なし) |
|
一般(市町村民税所得割額28万円未満) |
9,300円 |
- 通所施設等の食費負担について、所得の低い方はその一部が軽減されます。
- 入所施設を利用している方について、所得の低い方は食費や光熱水費等の実費負担が軽減されます。
- グループホームを利用している方について、所得の低い方は家賃の一定額が助成されます。
- 災害に遭ったとき等、申請により利用者負担を軽減できる場合があります。
- 利用者負担をすることによって生活保護の対象となる場合は、生活保護の対象ではなくなるまで負担額が軽減されます。
移動支援、日中一時支援(地域生活支援事業)利用者の利用者負担の上限月額
|
所得区分 |
負担上限額(月額) |
|---|---|
|
生活保護、低所得1、低所得2 |
0円(利用者負担なし) |
|
一般(18歳未満で市町村民税所得割額28万円未満) |
4,600円 |
|
一般(18歳以上で市町村民税所得割額16万円未満) |
9,300円 |
|
市町村民税課税世帯で上記区分に該当しない方 |
37,200円 |
(注意)障害福祉サービスおよび障害児通所支援にかかる利用者負担額を合算した額が上限額(月額)を超えないように軽減されます。
-
同じ世帯に、サービスを利用する方が複数おられる場合、合算した額が算定基準額を超えた分(同一の人が介護保険サービスを併用している場合、その利用者負担額を含みます。)は高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。(下記、「高額障害福祉サービス等給付費のご案内」をご覧ください)
障害児通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置
1.対象者
(1)市町村民税課税世帯で所得割額が77,101円以上の世帯
次の障害児通所支援を利用する小学校前児童が二人以上いる通所給付決定保護者
- 障害児通所支援を利用する小学校就学の始期に達するまでの障害児
- 幼稚園、特別支援学校幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設、認定こども園に通う小学校就学の始期に達するまでの児童
- 特例保育または家庭的保育事業等による保育を受ける児童
(2)市町村民税課税世帯で所得割額が77,101円未満の世帯
生計を一にする児童が二人以上いる通所給付費決定保護者
(子の年齢は問いません。18歳以上でも可。)
2.多子軽減制度適用後の利用者負担額
次表と利用者負担にかかる所得区分に応じた負担上限月額のいずれか低い額が利用者負担額となります。
|
区 分 |
多子軽減制度適用後の 利用者負担額 |
||
|---|---|---|---|
| 小学校就学後児童 | 軽減対象外 | ||
| 就学前児童 |
世帯の市町村民税所得割額 77,101円以上 |
兄姉が小学校就学前児童であって障害児通所支援利用児童が第2子のとき |
障害児通所支援の総費用の100分の5 |
| 兄姉が小学校就学前児童であって障害児通所支援利用児童が第3子以降のとき |
0円 |
||
|
世帯の市町村民税所得割額 77,101円未満 |
生計を一にする兄姉が1人いる | 障害児通所支援の総費用の100分の5 | |
| 生計を一にする兄姉が2人以上いる | 0円 | ||
3.手続き
(1)または(2)の必要書類をご準備のうえ、南部・北部障害者支援課に申請してください。
(1)所得割額が77,101円以上の世帯 :兄姉の通園等証明書
(所定の様式がありますので、南部・北部障害者支援課までお問い合わせください。)
(2)所得割額が77,101円未満の世帯 :住民票
(市内に住民票があり、申請書同意があれば省略可)
就学前の障害のある児童の児童発達支援等の無償化
就学前の障害のある児童への支援として、満3歳になって初めての4月1日から小学校に入学するまでの3年間は、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所支援、医療型障害児入所支援のサービス利用者負担が無料となります。
(留意事項)
- 利用者負担以外の費用(医療費や食費等実費負担しているもの)は、別途お支払いただくことになります。
- 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
- 別途、手続きは必要ありません。(障害児通所支援の受給者証に記載されます)
高額障害福祉サービス等給付費のご案内
制度の内容
同一世帯に障害福祉サービス等を利用する方が複数いる場合等に、世帯の負担を軽減する観点から、世帯における利用者負担額の合計(合算額)が一定の基準額を超えた場合に、申請により「高額障害福祉サービス費」「高額障害児通所給付費」「高額障害児入所給付費」を支給します(償還払い)。
世帯について
|
種別 |
合算の対象となる世帯の範囲 |
|---|---|
|
18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳は除く) |
障害のある方(本人)とその配偶者 |
|
18歳未満の障害児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民票上の世帯 |
合算の対象となる費用
- 障害者総合支援法に基づく介護給付費等に係る利用者負担額
(居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援など) - 介護保険の利用者負担額
(高額介護(予防)サービス費・高額医療合算介護サービス費により償還された費用を除く。ただし、同一人が障害福祉サービスを利用している場合に限る) - 補装具費に係る利用者負担額
(同一人が障害福祉サービス等を利用している場合に限る。ただし、平成24年4月支給決定分から対象となる) - 児童福祉法に基づく障害児通所給付費に係る利用者負担額
(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援) - 児童福祉法に基づく障害児入所給付費に係る利用者負担額
(障害児入所支援など)
支給される額
世帯における利用者負担額の合算額と基準額との差額が支給されます。
(世帯における利用者負担額)-(基準額)=(支給額)
【基準額】 37,200円
ただし、障害児の特例で、次のいずれかの場合は受給者証に記載されている負担上限月額のうち、最も高い額が基準額となります。
- 同一の障害児が根拠条項の異なる複数のサービスを利用している場合。
例)短期入所(障害者総合支援法)と放課後等デイサービス(児童福祉法)を利用している場合等 - 同一世帯にサービスを利用する障害児が複数おり、同一の保護者が支給決定を受けている場合。
一般(市町村民税所得割額28万円未満)の世帯における、障害児の特例の基準額
- 居宅・通所サービスを利用する場合:4,600円
- 施設入所サービスを利用する場合 :9,300円
支給事例
事例1:一人の障害児が、障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを利用している場合【基準額 4,600円】
※受給者証に記載されている負担上限月額のうち、最も高い額が基準額となります。
- (障害福祉サービス)利用者負担額:4,600円
- (児童福祉サービス)利用者負担額:4,600円
- <世帯における利用者負担額の合計>9,200円
- <支給される額>9,200円-4,600円=4,600円
事例2:同一世帯の障害児の兄弟姉妹が、障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを利用し、同一の保護者がその支給を受けている場合(補装具の支給なし)【基準額 4,600円】
Aさん
- (障害福祉サービス)利用者負担額:1,000円
- (児童福祉サービス)利用者負担額:4,600円
Bさん
- (障害福祉サービス)利用者負担額:1,000円
- (児童福祉サービス)利用者負担額: 0円
<世帯における利用者負担額の合計>6,600円
<支給される額> 6,600円-4,600円=2,000円
事例3:同一世帯の障害児の兄弟姉妹が、障害者総合支援法と児童福祉法のサービス、補装具を利用し、同一の保護者がその支給を受けている場合は2つの基準額にてそれぞれ算定します
【基準額1=4,600円,基準額2=37,200円】※補装具は障害児の特例の対象ではありませんのでご注意くだい。
Aさん
- (障害福祉サービス)利用者負担額: 0円
- (児童福祉サービス)利用者負担額:4,600円
Bさん
- (障害福祉サービス)利用者負担額: 4,600円
- (児童福祉サービス)利用者負担額: 0円
- (補装具費の支給) 利用者負担額:37,200円
1.事例3の場合は、障害福祉サービスと児童福祉サービスにかかる利用者負担額について、障害児の特例を適用します【基準額1=4,600円】
- <世帯における利用者負担額の合計>9,200円
- <支給される額>9,200円-4,600円=4,600円
2.残りの利用者負担額について算定します【基準額2=37,200円】
- <残りの世帯における利用者負担額の合計>4,600円+37,200円=41,800円
- <残りの支給される額>41,800円-37,200円=4,600円
事例4:一人の方が障害福祉サービスと介護保険サービスを利用している場合【基準額 37,200円】
- (障害福祉サービス)利用者負担額:30,000円
- (介護保険サービス)利用者負担額:30,000円
- <世帯における利用者負担額の合計>60,000円
- <支給される額>60,000円-37,200円=22,800円
手続きについて
南部・北部障害者支援課または各地区保健・福祉申請窓口、本庁障害福祉課に持参し申請してください。
- 個人番号(マイナンバー)の分かるもの。
- 振込先口座のわかるもの
- 領収書の写し(利用しているサービス全ての領収書。なお、食費や活動費などの実費負担分は制度の対象となりません)
- 補装具費支給決定通知書の写し(補装具の支給を受けている場合に必要です)
- 高額介護(予防)サービス費支給決定通知書、高額医療合算介護サービス費支給決定通知書の写し等償還金額がわかるもの(介護保険サービスを利用していて、支給を受けている場合に必要です)
なお、3,4,5を紛失等の場合は、申請明細書に申告のうえ申請書に添付してください。
申請時の注意点
- 介護保険サービスの利用者負担額は、高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費により償還された費用は含みません。
- 償還対象となるサービス利用月の翌月から5年を経過すると、時効により支給が受けられなくなりますので、ご注意ください。
- サービス利用者本人(障害児の場合は支給決定保護者)がお亡くなりになられた場合、相続人による申請はできませんので、ご了承ください。
申請書
申請書様式は、下記「【障害福祉サービス等】各種様式」ページ内、「15.高額障害福祉サービス等・障害児(通所・入所)給付費等支給申請書」欄からダウンロードしてご使用いただけます。
高齢障害者の介護保険サービスの利用者負担軽減制度
次のページをご確認ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 北部保健福祉センター 北部障害者支援課
福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
福祉局 福祉部 障害福祉政策担当
お住まいの地域がJR神戸線より北部の方
(北部保健福祉センター北部障害者支援課)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階
お住まいの地域がJR神戸線より南部の方
(南部保健福祉センター南部障害者支援課)
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階
障害福祉サービスの報酬の請求など
(障害福祉課)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:
06-4950-0374(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6415-6246(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6750(障害福祉課)
ファクス番号:
06-6428-5118(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6351(障害福祉課)














