65歳以上の人の保険料の納め方
印刷 ページ番号1004124 更新日 2025年4月1日
保険料算定開始月
介護保険の保険料は、第1号被保険者となった月(65歳到達月)の分から保険料の算定を行います。到達月とは、誕生日の前日の属する月をさします。例えば、誕生日が3月2日の人は3月から、3月1日の人は2月からとなります。
参考:国民健康保険に加入している人が65歳になり、年度の途中で第1号被保険者に変わられても、国民健康保険ではその年度の介護保険料分については、あらかじめ65歳到達月の前月分までの月数で計算しておりますので、第1号被保険者の保険料と重複することはありません。
保険料の納め方(特別徴収と普通徴収)
特別徴収(年金から天引き)と普通徴収(納付書払い、口座振替など)の2種類があり、原則、特別徴収による保険料納付となります。
特別徴収
年金が年額18万円以上受給見込みの人は、年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
特別徴収の対象となる年金には、老齢基礎年金・厚生年金・共済年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金・障害年金があります。(老齢福祉年金は除く)
なお、年金の年額が18万円以上受給見込みの人で本来は特別徴収の対象であっても、4月2日以降あらたに65歳になった人や尼崎市に転入された人は、初めは必ず普通徴収となります。
支給される年金と天引きされる保険料の関係
| 年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年金 | 2・3月分 | 4・5月分 | 6・7月分 | 8・9月分 | 10・11月分 | 12・1月分 |
| 保険料の天引き | 4・5月分 相当分 |
6・7月分 相当分 |
8・9月分 相当分 |
10・11月分 相当分 |
12・1月分 相当分 |
2・3月分 相当分 |
1. 2月は既に特別徴収の人で、4月以降も継続して特別徴収となる人の場合
2月分の保険料額と同額の保険料を4月・6月に差し引き、残りの保険料を8月・10月・12月と翌年2月に振り分けて差し引きます。
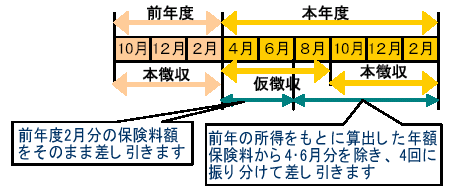
2. 4月から特別徴収(仮徴収)が始まる人の場合
昨年4月2日から10月1日までにあらたに65歳になった人や尼崎市に転入された人で、年金保険者(日本年金機構等)の通知により特別徴収の対象者と確認できた人は、市と年金保険者との特別徴収手続き完了に伴い介護保険料特別徴収(仮徴収)開始通知書でお知らせした仮徴収額を4月・6月に差し引き、残りの保険料を8月・10月・12月と翌年2月に振り分けて差し引きます。
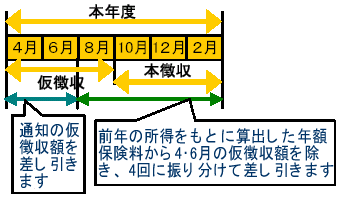
3. 6月から特別徴収(仮徴収)が始まる人の場合
昨年10月2日から12月1日までにあらたに65歳になられた人や尼崎市に転入された人で、年金保険者の通知により特別徴収の対象者と確認できた人は、市と年金保険者との特別徴収手続き完了に伴い介護保険料特別徴収(仮徴収)開始通知書でお知らせした仮徴収額を6月に差し引き、残りの保険料を8月・10月・12月と翌年2月に振り分けて差し引きます。
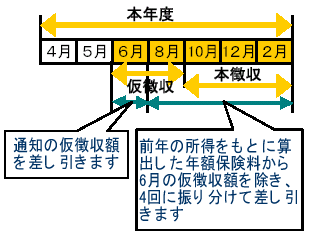
4. 10月から特別徴収(本徴収)が始まる人の場合
4月1日現在の被保険者、かつ年金保険者の通知により特別徴収の対象者と確認できた人は、介護保険料決定通知書による特別徴収(本徴収)額を10月・12月と翌年2月に差し引きます。
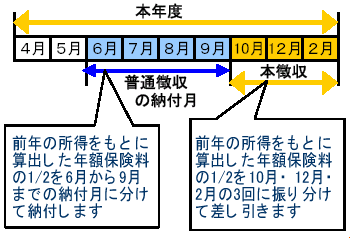
特別徴収の納め方が変更になるとき
特別徴収で保険料を納めている人の保険料額が、年度途中に変更となるなど、次のような場合には、納め方が変更になります。
- 保険料額が増額になる場合
特別徴収と普通徴収の両方で納めていただくことになります。 - 保険料額が減額になる場合
特別徴収から普通徴収に変わります。 - 年金保険者から天引きできないと連絡のあった場合
特別徴収から普通徴収に変わります。
補足:納め方が変更になった場合は、変更決定通知書をお送りしますのでご確認ください。
普通徴収
年金が年額18万円未満受給見込みの人は、送付される納付書や口座振替により、介護保険料を尼崎市に個人ごとに納めます。(年10回)
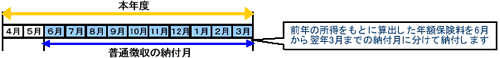
1. 4月1日現在被保険者で、年金を受給していない人や年額が18万円未満受給見込みの人の場合
年額保険料を6月から翌年3月までの納付月(年10回)で納付します。
2. 4月2日以降に、あらたに65歳となった人や尼崎市に転入された人の場合
資格取得日の月分から保険料が必要となります。なお、被保険者本人や世帯員の誰かが1月2日以降尼崎市に転入されている場合、前住所地の市区町村へ所得照会が必要となるため、保険料の決定が通常より遅くなります。
年度途中に尼崎市の第1号被保険者となった人は、年金保険者からの通知に基づいて、特別徴収が始まる年金支給月(下表参照)が確定できるまでは、普通徴収で納めていただきます。
|
年金保険者が次の期間に特別徴収の対象者となる人を抽出 |
特別徴収が始まる年金支給月 |
|---|---|
|
4月2日から10月1日まで |
翌年4月 |
|
10月2日から12月1日まで |
翌年6月 |
|
12月2日から翌年4月1日まで |
翌年10月 |
第1号被保険者の保険料減免制度
保険料を納めることが困難な場合は、申請により保険料の減免や徴収猶予を受けることができる場合があります。詳しくは下記のページをご覧ください。
介護保険料を滞納することにより、保険給付等に制限がかかります
保険料の納付が遅れ一定期間経過すると、督促状や催告書が送付され延滞金がかかります(督促手数料は令和7年4月1日以降分から廃止されました)。
さらに、当初の納期限から一定期間経過した保険料が一納期でもあると、特別な事情がない限り、その滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
1年間滞納すると
介護サービス・介護予防サービスを利用したとき、利用者が介護費用をいったん全額自分で支払わなければなりません。その後、申請して認められた場合は、保険給付分(費用の7割、8割又は9割)を介護保険から支払うという取扱いになります。これを保険給付に係る支払方法の変更(償還払い化)といい、一時的に多額の費用が必要となります。
1年6カ月以上滞納すると
一時的に保険給付分が差し止められます。この状態で引き続き保険料を納められないと、差し止められた保険給付分から滞納保険料に保険給付分を充てます。これを保険給付の支払いの一部差し止めといいます。
2年間滞納すると
保険料の納付は、通常2年で時効が成立し、保険料を納めたくても納めることができなくなります。(時効が成立すると、この滞納保険料を納めることはできません。)
時効になると、保険給付の割合が引き下げられます。サービスを利用するときの利用者負担が、1割又は2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられます(給付額減額措置)。また、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費及び特定入所者介護サービス費は支給されなくなります。なお、こうした扱いになる期間は、未納期間(額)に応じて決まりますので、時効になった保険料以外の保険料に滞納が少ないほどその措置期間は短くなります。
補足:
- 高額介護サービス費とは、同一世帯の利用者が同一月に利用した介護サービスの利用者負担額の世帯合計が一定の上限を超えた場合に、超えた額が支給される制度です。
- 高額医療合算介護サービス費とは、各医療保険における世帯内で、1年間の医療保険と介護保険それぞれの自己負担を合算した額が一定の上限を超えた場合に、超えた額が支給される制度です。
- 特定入所者介護サービス費とは、低所得の人が介護保険施設(短期入所を含む)を利用するときに、食費と居住費については申請により一定額を超えた分が保険で給付される制度です。
- 介護保険料は、介護保険法の規定により被保険者の世帯主及び配偶者にも、連帯して納付する義務があります。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
メールアドレス:ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp














